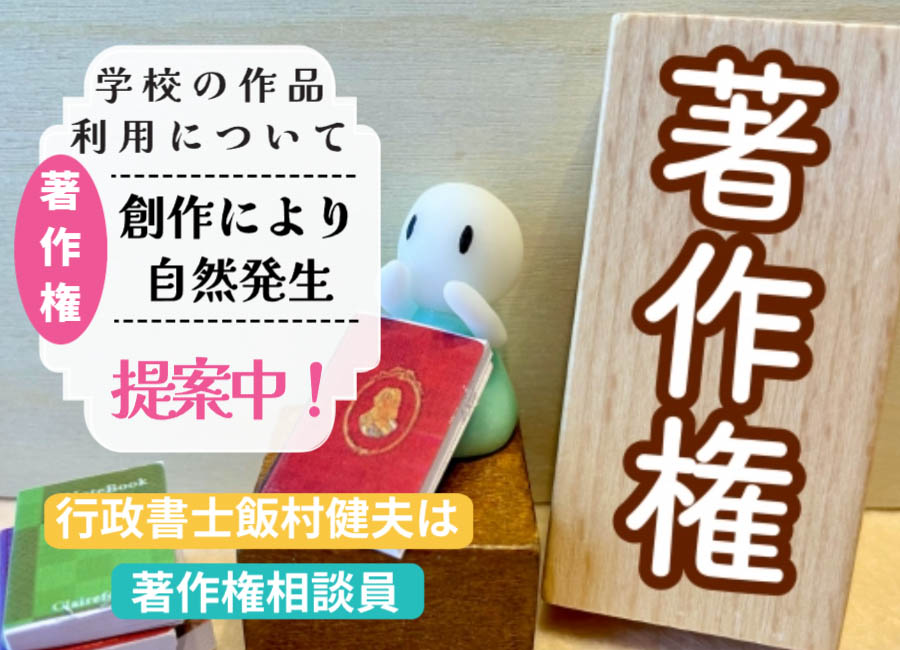
学校における著作権
行政書士飯村健夫は、著作権相談員として登録されてます
- 文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
著作権は、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生
- 著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
教育機関における、作品利用について
- その公共性から、一定の範囲で自由につかうことができます。
- 学校の教育活動において、著作権の問題は避けて通れません、 コロナ禍において、リモートやオンデマンドの教育が行われた ことにより、著作権を意識して教育活動を行うことが、とても 重要になりました。
著作権を侵害しないために学校が行うべき取り組みについて、以下のように提案します。
1. 教職員の著作権教育の強化
著作権を理解し、実践するためには、まず教職員が正しい知識を持つことが必要です。教師自身が著作権について理解していないと、適切な指導が行えません。したがって、定期的な研修やセミナーを開催し、著作権に関する法令、判例、そして具体的な実践方法について学ぶ機会を提供します。
2. 学生への著作権教育の徹底
学生に対しても、著作権の重要性を理解させることが必要です。具体的な取り組みとして、以下のような方法があります:
- 授業内での指導:国語や社会の授業で著作権に関する単元を設け、著作権法の基本を学ばせる。
- プロジェクト学習:調査レポートやプレゼンテーションを通じて、正しい引用方法や二次創作のルールを実践させる。
- デジタルリテラシー教育:インターネットの利用が進む現代において、デジタルコンテンツの利用に関するリテラシー教育を行う。
3. 適切な引用方法の指導
著作権侵害を避けるためには、適切な引用方法を学生に教えることが不可欠です。引用の基本ルールを明確に示し、実践的な例を使って具体的な引用方法を指導します。たとえば、以下のポイントをカバーします:
- 引用の範囲:引用する部分の範囲を明確にし、必要最低限の引用にとどめる。
- 引用元の明示:必ず引用元を明示し、引用部分と自身の意見や考察を明確に区別する。
- 引用の目的:引用はあくまで補足的な情報提供や参考のためであり、主要なコンテンツとして使用しない。
4. デジタル教材の利用と管理
デジタル教材の利用が増える中で、著作権侵害を防ぐための対策も重要です。以下の取り組みを推進します:
- ライセンスの確認:利用する教材が適切なライセンスの下で提供されていることを確認し、無断使用を避ける。
- オープンエデュケーショナルリソース(OER)の活用:著作権フリーの教材やオープンライセンスの教材を積極的に活用する。
- デジタル著作権管理(DRM)の理解:DRM技術を用いて、著作権保護されたコンテンツの適切な利用方法を指導する。
5. 学校内での著作権ガイドラインの整備
学校全体で著作権に関する統一的なガイドラインを策定し、教職員および学生に周知徹底させることが重要です。以下のような項目を含むガイドラインを作成します:
- 著作権に関する基本方針:著作権法の遵守を明示し、学校全体での取り組みを促す。
- 教材作成および利用のルール:教職員が自作教材を作成する際の著作権の扱いや、外部教材の利用に関するルールを明確化する。
- 違反時の対応:著作権侵害が発覚した場合の対応策やペナルティを明示し、予防および再発防止に努める。
6. 学校図書館の役割
学校図書館は、著作権教育の一環として重要な役割を果たします。以下の取り組みを行います:
- 著作権に関する資料の整備:著作権に関する書籍や資料を揃え、教職員や学生が自由にアクセスできるようにする。
- ライブラリセッションの実施:図書館司書が著作権に関するセッションを定期的に開催し、利用者に適切な情報を提供する。
7. 継続的な監視と改善
著作権に関する取り組みは一度で完了するものではありません。定期的に実施状況を監視し、必要に応じて改善を行います。以下の取り組みを推進します:
-
- モニタリング:定期的に著作権の取り組み状況をチェックし、不適切な利用がないか確認する。
- フィードバックの収集:教職員や学生からのフィードバックを受け取り、取り組みの改善に活かす。
- 最新情報の共有:著作権に関する法改正や新たな判例について情報を収集し、適時に学校全体で共有する。
記載の事項は、文化庁の資料に基づいて記載されています。

